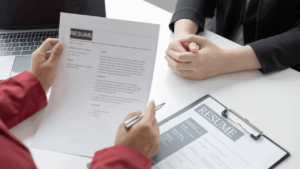日本では「アロマ=いい香り」というイメージが定着しています。
疲れた時にラベンダーの香りを嗅いでホッとした経験がある方も多いのではないでしょうか?
しかし実は、精油には“香りを楽しむ”以外にも、体にしっかりと働きかける力があります。
この記事では、精油が私たちに与える2つの影響、「嗅覚作用」と「薬理効果」の違いについてご紹介します!
1. 香りを嗅ぐことで得られる「嗅覚作用」とは?
まずは、私たちが普段感じている“いい香り”が、脳や体にどのように作用しているのかを見てみましょう。
香りの分子は、鼻の奥にある「嗅上皮(きゅうじょうひ)」という場所に届きます。
そこには嗅覚受容体があり、香りをキャッチすると、それが電気信号となって脳へ伝わります。
このとき、信号が届くのは「大脳辺縁系(だいのうへんえんけい)」という、感情や本能をつかさどる部分。
さらに「視床下部(ししょうかぶ)」という、自律神経やホルモンバランスに関係する場所にも影響を与えます。
つまり、香りを嗅ぐことで
- 気分が落ち着く
- リラックスできる
- やる気が出る
など、主に精神面・感情面への作用が期待できるのです。
この反応はとても早く、香りを嗅いで数秒以内に脳が反応します。ただし、持続性はそれほど長くありません。
▶︎嗅覚作用のまとめ
- 【伝達ルート】:鼻→脳(大脳辺縁系、視床下部)
- 【作用】:感情・気分・自律神経に影響
- 【即効性】:あり
- 【持続性】:短い
2. 皮膚に塗ることで得られる「薬理効果」とは?

次に、精油を“塗布する”ことで得られる作用について見ていきます。
精油は植物から抽出された高濃度の成分を含む液体です。その成分は非常に小さな分子構造を持っており、皮膚に塗ると毛穴や皮脂腺から皮膚の内側に入り込み、毛細血管にまで届きます。
血液に乗った精油成分は、全身を巡って各臓器や細胞に働きかけ、例えば以下のような身体的な作用をもたらします。
- 抗炎症作用(例:痛みや腫れをやわらげる)
- 鎮痛作用(例:頭痛や筋肉痛の緩和)
- 抗菌・抗ウイルス作用(例:風邪予防)
- ホルモン調整作用(例:月経や更年期症状のサポート)
香りのような即効性はありませんが、継続して使うことで心身のバランスを整えていく力があります。
▶︎薬理効果のまとめ
- 【伝達ルート】:皮膚→血流→全身の臓器や細胞
- 【作用】:身体機能・ホルモン・免疫などに影響
- 【即効性】:ややゆっくり
- 【持続性】:長い
3. 嗅覚反応分析で活用していくのは?
ここで、「嗅覚反応分析」についてご紹介します。
嗅覚反応分析とは、8種類の香りを嗅いで好みの順に並べることで、体質や心身の状態を分析する手法です。
これは、香りの好みが、体が必要としている成分を本能的に選んでいるという理論に基づいています。
分析の結果をもとに、その人に合った精油を提案し、「塗布(皮膚塗布)」することも取り入れて
心と体のバランスを整えるのが、嗅覚反応分析の一つの特長です。
つまり、ただ“いい香りを嗅ぐ”のではなく、“今の自分に必要な成分を選び、それを取り入れる”という視点で精油を使っていきます。
もちろん、その方に合った食事や運動、生活習慣なども見えてきますので、それらも合わせてアプローチしていきます。

4. なぜ「香りを嗅ぐだけ」では足りないのか?
冒頭でお伝えした通り、日本では「香りを楽しむ」ことに注目が集まりがちです。
そのため、「毎日好きな香りを嗅げばいいのかな?」と誤解されることも少なくありません。
ですが、本当に心身の不調を整えたいとき、香りだけでは効果が限定的なのです。
嗅覚作用はたしかに気分を変えるパワーがありますが、それだけでは根本的な体質改善にはつながりにくいことがあります。
その点、薬理効果は
- 体の内側からのサポート
- 成分の持つ機能性による作用
が期待できるため、長期的なケアや体質改善に有効です。
5. まとめ:香りを楽しむ+“使う”で、精油の力を最大限に
精油には「香りで気分を変える」力も、「成分で体に作用する」力もあります。
でも、もし本気で体調を整えたい・今の不調を改善したいと感じているなら、 “嗅ぐだけ”ではもったいないのです。
嗅覚反応分析では、香りを通じて今の自分を知り、その結果に基づいて、体に働きかける“塗布”という使い方を提案しています。
これから精油を使ってみたい方も、すでにアロマに親しんでいる方も、
「香り+薬理効果」の両方を知ることが、精油を“活かす”第一歩になります。
ぜひ、ご自身の体質に合った香りを、上手に使ってみてくださいね。