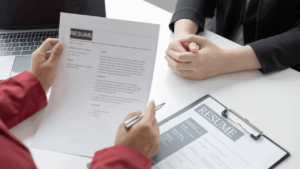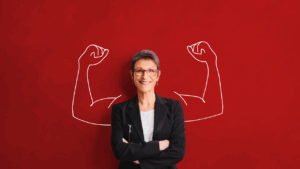精油は香りを嗅ぐだけじゃない!フランス式アロマに学ぶ体に効かせる本当の使い方
「アロマ=リラックス」が日本で広まった歴史的背景
「精油」と聞いて、あなたはどんなイメージが浮かびますか?
多くの方は、
「ディフューザーで香らせてリラックスするもの」
「アロマキャンドルを灯して癒やされるもの」
といった、香りを楽しむイメージを持たれるでしょう。
このように、日本においては香りで癒やしを得る「イギリス式アロマセラピー」が主流になっています。
これには歴史的な背景があります。
そのため、日本ではこの著書に基づいて「香りを楽しむ=アロマテラピー」というイメージが深く根付いていったんですね。
香りを嗅ぐだけでは得られない身体への作用
良い香りの精油を嗅ぐと、「いい香り」「落ち着く」と心理的な効果を得ます。
これは、嗅覚が脳の感情や記憶を司る部分にダイレクトに届くから。
私たちが嗅覚反応分析で香りの好みをチェックするときにも、この本能的な仕組みを使っています。
ただし、香りを嗅ぐだけでは、血流を促す、筋肉をゆるめる、免疫をサポートするといった身体的な作用は、残念ながらあまり期待できません。
「良い香り=リラックス」は間違いではないけれど、それはあくまで心に響く効果が中心なんです。
フランス式アロマ:「体に塗る」メディカルな使い方

一方、フランスでは植物成分の効果を期待した、いわゆる「メディカル・アロマテラピー」と呼ばれるアプローチが発展しました。
フランスでは1927年に「アロマテラピー」という言葉が生まれ、医師が臨床で精油を使うなど、その薬理作用を重視したフランス式が発展していったんです。
ここでは、香りを嗅ぐだけでなく、精油を適切に希釈して体に塗布するといった使い方が主流です。
たとえば、肩こりにローズマリーを塗ると血流が促される効果が期待できたり、風邪の季節にティートリーを胸元に塗ると呼吸が楽になる感覚があったり。
こうした体に働きかける使い方は、香りを嗅ぐだけでは得られない精油のもう一つの力です。
塗布が身体に効く!精油成分が届くメカニズム
なぜ、体に塗るだけで精油の力が発揮されるのでしょうか?
精油は分子が非常に小さいため、適切に希釈して皮膚に塗布すると、その成分が皮膚を通り抜けて、毛細血管から血流に乗って全身に届くんです。
この血流に乗るというプロセスが、心と体のバランスが崩れた時に起こりがちな、血行不良や筋肉の緊張といった生理的な作用をサポートするために非常に重要になってきます。
日本に広まったのはイギリス式からでしたが、フランス式の「精油の成分効果を期待した使い方」は、心身の土台から整えたい40代・50代の私たちにとって、ぜひ知っておきたい知識です。
嗅覚反応分析が塗布を整えの中心とする理由
私が行っている嗅覚反応分析でも、結果のグラフをもとに、心身が今欲している成分を精油から借りるために、塗布を整えの中心として採用しています。
この場合、単に不快な症状に対して直接アプローチするのではなく、心身が求めている特定のエネルギーバランスに働きかけるのが目的です。
「いい香りだから癒やされる」の先に、「体に効かせて根本から整える」というステップがある。
その違いを知るだけで、精油の世界はぐっと広がり、あなたのウェルビーイングを支える頼もしい相棒になってくれますよ。
まとめ:精油を身近な相棒にするための知識
精油は、「香って癒やす」だけのアイテムではありません。
塗布という使い方を知ることで、血流や生理的な作用をサポートする力を引き出すことができます。
アロマ=リラックス、というイメージが広まったのは、歴史的な経緯によるもの。
ですが、フランス式アロマが示す「体を整えるケア」の視点を取り入れると、精油はぐっと身近で頼もしい相棒になってくれるはずです。
香りを楽しむ、さらにその先の体を整えるケアへ。
その一歩を、一緒に踏み出してみませんか?